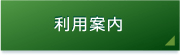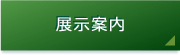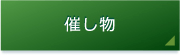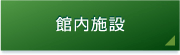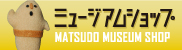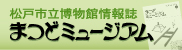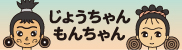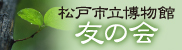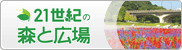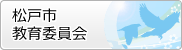館長室から
松戸市立博物館長 渡辺 尚志
挨拶
2022年4月から館長に就任しました、渡辺尚志と申します。専門は日本近世史(江戸時代史)で、江戸時代の村と農民の歴史についてずっと研究してきました。
私は約30年前から松戸市に住んでいますので、松戸市の近世についても少しずつ研究しています。具体的な成果としては、幸谷村(現在の新松戸駅周辺)を取り上げた『殿様が三人いた村』(崙書房出版、2017年、現在は絶版)、『言いなりにならない江戸の百姓たち』(文学通信、2021年)を刊行しました。また、論文集『近世の村と百姓』(勉誠出版、2021年)のなかにも、幸谷村を対象とした論文を収めています。松戸市域以外を扱った最近の出版物としては、2022年4月に『武士に「もの言う」百姓たち』が草思社文庫から再刊されました(初版は2012年)。これからもさらに松戸市域の歴史研究に力を入れ、その成果をわかりやすく皆様にお伝えしていきたいと思います。
経歴
1957年、東京都生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。一橋大学名誉教授。専門は日本近世史・村落史。
著書
- 『松戸の江戸時代を知る(1) 小金町と周辺の村々』(たけしま出版、2023年)
- 『松戸の江戸時代を知る(2) 城跡の村の江戸時代』(たけしま出版、2023年)
- 『松戸の江戸時代を知る(3) 川と向き合う江戸時代』(たけしま出版、2024年)
- 『百姓たちの江戸時代』(ちくまプリマー新書、2009年)
- 『百姓の力 江戸時代から見える日本』(角川ソフィア文庫、2015年)
- 『海に生きた百姓たち』(草思社文庫、2022年)
テレビ出演
- NHK BS「英雄たちの選択」(BS4K:2024年11月7日 20時から、BS:2024年11月11日 21時から)
最新!小林一茶と松戸(1)(2025年8月4日)
我と来て遊べや親のない雀
痩蛙まけるな一茶ここに有り
雀の子そこのけそこのけ御馬が通る
やれ打つな蠅が手をする足をする
皆様のなかには、これらの句を知っている方も多いでしょう。これらは、いずれも江戸時代の俳諧師(俳諧を本業とする人)・小林一茶の句です。一茶は、農民の生活感情や江戸下町に生きる人々に寄り添い、庶民の目線で句を詠みました。彼の句は滑稽味豊かであるとともに、子どもや動物など対象への慈愛に満ちています。そして、一茶は現松戸市域と深い関わりがありました。それをお話しする前に、今回は一茶の生涯について簡単に述べましょう。
一茶は、宝暦13年(1763)5月5日に、信濃国水内郡柏原宿(現長野県上水内郡信濃町)の百姓弥五兵衛の長男として生まれ、弥太郎と名付けられました。
母の「くに」は、弥太郎が3歳のときに亡くなり、以後彼は祖母「かな」に育てられました。弥太郎が8歳の明和7年(1770)に、父が「さつ」と再婚しました。弥太郎が10歳だった安永元年(1772)に弟仙六が生まれ、安永5年に祖母が亡くなると、継母「さつ」との不和が決定的なものになりました。
そこで、弥五兵衛は、もう弥太郎を家には置いておけないと判断し、弥太郎15歳の安永6年(1777)春に、彼を江戸へ奉公に出しました。それから10年後の天明7年(1787、弥太郎25歳)まで、彼の消息ははっきりしません。25歳のときには、弥太郎は、すでに俳諧師として生きていく決心を固めていました。そこで、以後は彼を一茶と記します。
一茶は、寛政10年(1798)から、本所・深川(現東京都墨田区・江東区)あたりで借家住まいをしながら、下総(現松戸市域を含む千葉県北部)各地の俳人(俳諧愛好者)たちの所を廻るようになりました。この頃から、現松戸市域の人々との交流が本格化していきます。
一茶はしだいに江戸で俳諧師として名が知られるようになりますが、生活は相変わらずの借家暮らしで不安定なままでした。そこで、彼は、郷里の柏原宿に帰ることを考え始め、51歳の文化10年(1813)に柏原宿に家を構えました。それでも、文化14年までは房総(現千葉県)各地を廻っていましたが、文化15年以降は信濃国を拠点として、房総に来ることはなくなりました。ただし、以後も房総の俳人たちとは手紙のやり取りを続けています。
晩年の一茶は、老いと病に悩まされつつも精力的に句作を続けましたが、文政10年(1827)に亡くなりました。
次回からは、一茶と現松戸市域とのつながりについて述べていきます。