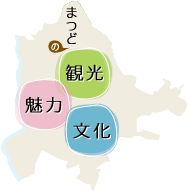水とみどりと歴史の回廊マップ(松戸地区)
徳川家康の江戸入府後、しばらくの間の松戸は、人口も少なく「松戸村」と呼ばれていました。
松戸村に寺院が建立され始めるのは慶長14年(1609年)頃からで、松戸村七ヶ寺院がつぎつぎと建立され、徐々に村としての力を得てきました。
そして、天領となった元禄12年(1699年)頃、江戸の発展の影響を受け、街の規模はさらに大きくなり「松戸町」となり、宝暦13年(1763年)には「松戸宿」と呼ばれるようになりました。
松戸村は、江戸川を挟んで江戸と相対し、川の江戸方に「金町松戸関所」が置かれ渡船場を控えた宿場として、また、徳川幕府による江戸水防の一環とした江戸川の整備により水上輸送の経由地としても活況を呈しました。
今でも多くの寺社が往時を偲ばせてくれます。また、松戸神社周辺の坂川では、「カワズザクラ」や「シダレザクラ」を植樹した散策路が整備され、かつての清流もよみがえりました。
いにしえに想いを馳せながら「水とみどりと歴史のまち」旧松戸宿周辺を散策してみませんか?
- 水とみどりと歴史の回廊マップ(松戸地区)~歴史・Part1~
- 水とみどりと歴史の回廊マップ(松戸地区)~歴史・Part2~
- 水とみどりと歴史の回廊マップ(松戸地区)~水とみどり~
- 水とみどりと歴史の回廊マップ(松戸地区)~お祭り~