貸借対照表の作成プロセス
更新日:2013年11月25日
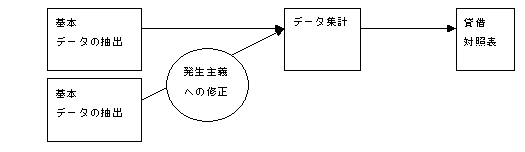
貸借対照表は、各科目の該当データをそれぞれの資料から作成する。その後、歳出、歳入に含まれているが資産、負債として認識されていないものを選択し、発生主義で計算した場合の金額を計上する。
基本データからの修正が必要な科目には、貸倒引当金、有形固定資産、退職給与引当金等がある。
これらの科目については金額の算定に当たって、以下の修正を行う。
(具体的な計算は各科目説明参照)
(1)有形固定資産の減価償却
施設、備品および車両等の有形固定資産の取得に要した支出額を、その支払時に全額コストとして計上するのではなく貸借対照表に資産として計上するとともに、有形固定資産の利用に応じた経済耐用年数に渡ってコストとして期間配分し、それに応じて資産の価値を減少させる手続きをとる。
(2)退職給与引当金
職員の退職手当に関する支出額を、その支出時に全額コストとして計上するのではなく、職員の勤務に応じて発生するものと考え、あらかじめその支出額を見積り、貸借対照表に負債として計上する手続きをとる。
(3)貸倒引当金
収入未済額、貸付金等の残高のうち、将来不納欠損として処理される可能性のある部分について、あらかじめその回収不能額を見積もり、資産のマイナス勘定として貸借対照表に計上する手続きをとる。
(4)修繕引当金(試作では修繕引当金の計上は行っていない)
定期的に実施される施設の大規模修繕に関する支出額を、その支払時に全額コストとして計上するのではなく、修繕は施設の利用に応じて発生するものと考え、あらかじめその支出額を見積もり、貸借対照表に負債として計上する手続きをとる。


